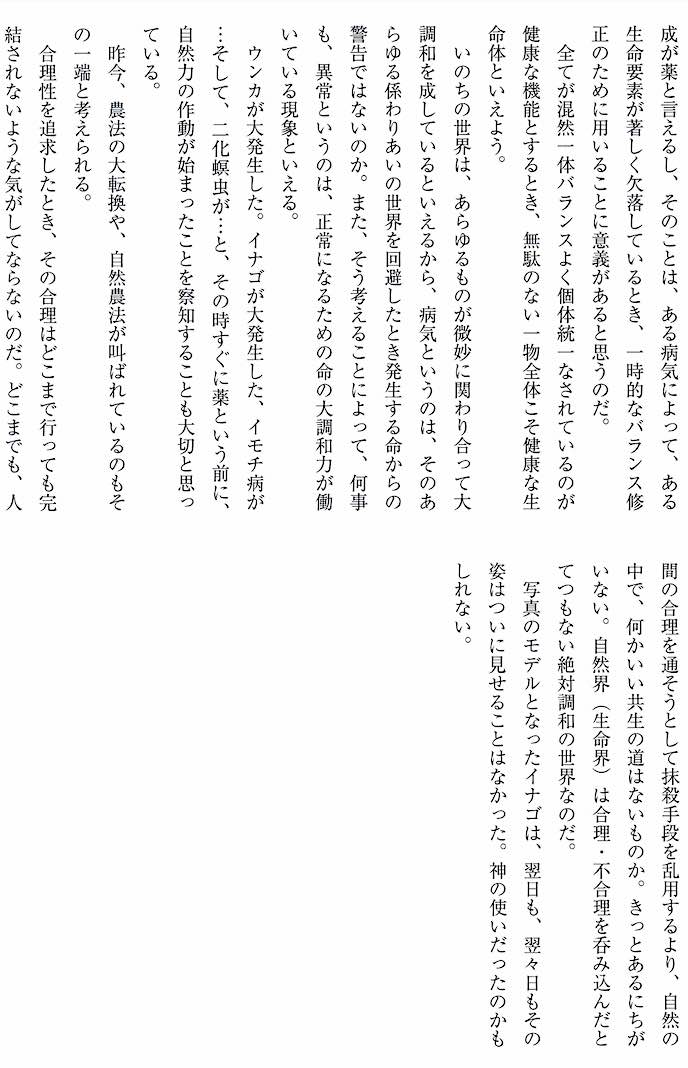本の詳細
本の要点・概要
 減反休耕田に自生した稲穂の越冬
減反休耕田に自生した稲穂の越冬
便利な生活を享受するために、工業を中心にしてひた走ってきた日本社会。そのいっぽうで、むかしもいまも、ずっと変わらずいのちの原点でありつづける食のふる里。個人の生き方として、また社会の健全な姿としてのバランスを、どうやって回復したらよいのでしょうか。主に山間の農村風景の写真とともに思いをつづっています。

本文からの抜粋
生きる原点、また、心の原点ともいえるいのちのふる里が、社会の中心軸になって、回ってほしいという思いに今も変わりはない。
「まえがき」の一節
まえがき
一〇代から今日までの六〇年あまり、私の身辺から離れることのなかったカメラとその機材は、単なる趣味の域でありそれを越すものではなかった。
ところが、平成七年ころから意識的に撮り残したい衝動に駆られるようになったことがある。それは、農村地帯(主に山村地帯)を撮影することであった。これからの農業環境が急カーブを描いて変化することを思い、今こそ残しておきたいモチーフであると思った。
その原因といえば、酒好きの私は酒が禍となって、ついには、意識転換を余儀なくされ、その価値観が一変したことである。
価値観が逆転してみると、現実社会を見る目も逆転していることに気づくことになった。私の見る目は、現実の裏面からの視点へと変化をし、そのために、どうも批判的になる傾向が強くなった。社会に恨みつらみがある訳ではないのに、むしろ、自分の内面にこそその的があったといえる。
酒のために考えを変えてみると、そこには、酒の親ともいえる「米」という人のいのちを支える主食という問題にぶち当たり、人のいのちと心(実際は自分のいのちと心)を探求する毎日となった。そのため、私の目の前には常に米(農業)があり、そして、人が生きること、さらに、調和円満に生きたい社会像があった。
社会の裏面からの視点は大分薄れてきて現実感が濃くなったが、この随想を記したころはその絶頂期でもあった。一歩外に出て農村地帯を廻ると荒れ放題の減反休耕田が目に飛び込んでくる。片や、主食の米を含めて日本の食料品の七〇%程が外国に依存する時代だという。これは大変深刻なことだと悲痛に考えるようになった。
所詮、犬の遠吠え感ではあるが、写真撮影と共に率直な自分の思いを書いてみたかった。この随想の原文は平成八年にノートしたものである。
人の生きる原点、また、心の原点ともいえる山・川・田(畑)・人(農)といういのちのふる里が、社会の中心軸になって、回ってほしいという思いに今も変わりはない。
菅原 茂
思考の世界では主観と客観に分離出来るが、いのちの世界から見るならば主観も客観もなく世界は一つだ。
「いのちのスクリーン」の一節
いのちのスクリーン
自分のいのちは、他のいのちと霊線(命の光)でつながっていることがそれとなくわかる。
原始の単細胞時代から永々時の流れの中で進化し続け、ついに、現代人の姿まで変化した。これまで発生した全ての生命世界には、どれ一つとして、命のつながりに無縁のいのちはないはずだ。
どれほどあるか夥しい数の〝種〟があって、更に膨大な数の〝個〟が存在する。ところが、生命エネルギーの本流から見たなら、どれ一つとつても別世界の命の持ち主はいないと思うのだ。それは、宇宙から発せられた地球の命の流れであり、この宇宙以外の世界からの生命は考えられない。
いのちの本体のことを命の光と言えるなら、この世の森羅万象は、命の光を本体にしてみな平等不滅の光を発していることになる。人間だけが別世界の命なのではあり得ない。働きは異なるとはいえ、命の光はみな平等にして変わりない光を発している。
この世一切が命の光で結ばれているなら話は早い。外の世界一切と自分とはみな不離一体同根の光だ。しからば、目前の風景にせよ、みな自分のいのちの中に存在していることになる。
いのちのルーツを遡及したとき、風景の一部始終に自分の命が結ばれている仕組みがわかってくるし、それは、生命同根のいのちの持ち主たちであるから理屈もない。
内なる自分の世界は、実際にこの目で見ている風景そのものであるわけだ。
風景が自分だなどと言えばいよいよ狂気じみてくるが、理屈なく本当の世界なのだ。
思考の世界では主観と客観に分離出来るが、いのちの世界から見るならば主観も客観もなく世界は一つだ。外の世界と自分は完全に分離していると考えがちだが、いのちの世界からみた時そうではなくなる。内なるスクリーンには常に外の世界が映し出されているのが真実の姿だ。
〝内は外なり、外は内なり
主観は客観、客観は主観なり〟
ということになる。
この考え方は、あくまでもいのちという万物共通の観点からであり、心の問題はまた別のことである。
〝山襞深く
雪また深く
燃え立ついのちは
大地の中
寂寥深々草木眠りて
春の目覚めは
まだ遠い〟
雪国の写真一枚見るにしても、それは、常に、命のスクリーンに依存する光景なのだ。
われわれは、発する思考力を停止して、無想の境地になった時、客観の風景は、内なる風景と合致する。外が内になり、内が外になった時、いのち本流からの波動と共振共鳴の感動が湧き上がる。激しい感動のひびきが沸き起こる。そこが、
〝いのちのふる里だ〟
山があって
川が流れ
ほとりに
耕しつづけた
田圃があって
点々と
家があって
そこで暮らす
人々がいる
人々はその得意分野を伸ばし完全分業化へとその姿を変えて行く。そして、ふる里の自給生活は次第に半自給へそして他給生活への道をたどる。
「米はいのちの玉手箱」の一節
米はいのちの玉手箱
めったに見かけなくなった残雪…。ここは深い深い雪の国。春はまだ遠いふる里であるが、ところによってはちょっぴり田圃が顔を出している。数えるほどの稲株をのぞかせ、やはり春の便りは足元まで響き出していた。
日中だというのに人影は目に入らず一層山の深さを感じさせる。そこには長い自給生活の温もりがあった。
夜はランプの明かり、燃料は植物油や動物の油でよい。暖房には薪があり、少し下ったところには澄んだ川が流れている。
農具類や生活必需品は天然の草木類を用いて加工する。石や岩なども色々と役に立つ。中には必ず手先の器用な人がいたから自給生活はつい近年までのことであった。
後に、人々はその得意分野を伸ばし完全分業化へとその姿を変えて行く。そして、ふる里の自給生活は次第に半自給へそして他給生活への道をたどる。
人は人を頼りにし寄りどころとして生きてきた。一人で何もかもやらねばならない自給自足の時代は遠くへ過ぎ去った。それが為にこの世は経済優先となり、物品流通の媒体として貨幣を最重視するようになった。金は神様となり、金に群がる人の心は欲を中心に先走り紛争が絶えることがない。欲望媒体の貨幣は怪物の独り歩きに見えてくる。
それでいいというならそれまでだが、こうなってくると人の世は一種の浮草現象のようで危なっかしい。一年一作二作の農業には見向きもしなくなる傾向を生む。
自然時間と共存する食料世界の農村は、科学的応用の利く工業系世界とは根本的にその次元が違う。
都市化が進み、人口集中が激しくなればなるほど、社会構造も複雑多岐となり、なにかと知性も人心もこんがらかってくる。
テンポの速い機敏に動く頭で工業系をすすめ、情報機能を複雑にしてそこに金が絡み付く。人は鉄を食って生きねばならぬのか…人は情報を食って生きねばならぬのか。心の方向は、生きる原点・いのちのふる里ではなく、金のなる木の山を追い求める世界となりがちだ。
人は鉄を食っても、情報を食っても生きられない。
いのちの光は
山と川と田圃と
そこに住む
農人の魂から光りだす
米は天地の贈り物
いのちの玉手箱
全ての生物が平等に存在するためには、その「種」に与えられた天与の食物が定められていて当然だ。
「食い改めて百歲長寿」の一節
食い改めて百歲長寿
稲作の歴史はわかっているだけでも、今から七千年以上も前に遡るという。七千年前には稲作文化が花開いていた、という中国〝河姆渡遺跡〟博物館長の話もある。
〝人間と米は一心同体の命の花
米は人なり…人は米なり…〟
と、少し気張った感じがあるけど、御飯党員(?)の私は朝昼晚〝玄米党員〟でもある。
五榖の中心である米は、人類救済の救世主だ。救世主、即ち〝メシア〟とはご飯こそ、〝メシア〟(飯やぁ)である。
悔い改めるとは〝食い改めよ〟の米のことをまず生きる原点から考え直したい。
いのちには自然治癒力という中心作用があって、常に安定を保つような生理調節機能が働いている。それが順調に働くために、また、生命機能を妨害しないためにも、自分自身の、心と体の浄化に気を配っている。
いのちは、天の気(呼吸)と、地の気(食)の反復継続によって保存される。地の気は即ち米たち五穀や野菜等の生命エネルギーを吸収して五体生命を保ち、今日のいのちを生かされる。当たり前のことだが、普段は心がとどかない。
この地球上には何千万種の生物が存在するといわれるが、その生命維持エネルギー源としての食物摂取には、見えざる厳然とした掟のようなものがあるといっていい。いわゆる食物連鎖と呼ばれているものであり、手当たり次第殺し合って、何でも食べるということは出来ないであろう。全ての生物が平等に存在するためには、その「種」に与えられた天与の食物が定められていて当然だ。食い物の争いは命懸けで、食糧問題は戦争にまで発展するではないか。医学者であり、文化勲章受章者でもある〝二木謙三〟先生は、次のように述べられている。
「今日の医学は、完全正食を無視した医学である。完全正食とは、蚕に桑の葉、鶴にドジョウ、鷹に雀、猫に鼠、虎に兎、日本人には玄米菜食で、それでこそ天地は生成化育で、人は自然順応で、天地に矛盾なく、人生に病無く、人は無病、無苦、無痛、安楽な死をとげることができるのである」と。
先生は、著書『健康への道』のプロローグに記している。昭和一七年に書かれた本であるが、「日本人には玄米菜食を」ということに、今こそじっくり耳を傾け、真剣に取り上げたい時代ではないのか。
国家医療費が三〇兆円(平成一〇年度)ともいわれ、内、一〇兆円位が老人医療費に呑み込まれているという実情は、それだけ、老人の生きざまの悪化を示しているようでならない。
これからは、食生活を「食い改めて」、健康な心と体で人生を過ごしたいものだ。そのことは、取りも直さず
いのちのふる里に振り返り
生きる原点に振り返り
都市的、商工業的
情報的偏重から振り返り
いのちのふる里〝農業〟を
見つめ直す思いやりが
大切なことだ
農の心は天地の心
天地の心は人の道
だと、しみじみ思うのである。
人は、コンピューターや宝石を食うわけにはいかない。
「祖先のエッセンス」の一節
祖先のエッセンス
どこを歩いて見ても現代建築にいろどられ、昔の面影はその姿を消した農村風景その中にあって、時代を忘れたかのような一軒の茅葺き屋根がその姿を見せてくれた。泰然微動だにせぬその風格は、時代を呑み込み静かにその光彩を放っていた。
家の前は断崖絶壁で川の流れに足を伸ばしていた。
昨年一一月のこと、減反休耕田に自生する稲探しの時、この家の裏の田圃から雑草に混じっている二~三本の稲穂を発見している。家の名前も印象深く道路に面した入り口には重厚な門柱が建っていてそこに表札が据えてあった。
名は「〇〇安兵エ」
と刻まれていて、歴史とその人格をも漂わせていた。
人間の知性は爆発的で急流となって過ぎてゆく。が、このお宅の自然流は見るだけで安らぎを感じさせてくれる。そこに慌ただしい時間はなく自然と一体でゆるやかだ。
生きるため食物はその母体を大地以外に求めることは出来そうもなく、その母体と茅葺き屋根はあまりにもぴったりなのだ。
現代は、地球一周秒速の速さで情報が流れるご時勢だ。流行とその多様性と情報速度はしたたかな商業べースに乗って回転するから、人はこの流行に一種の幻惑を感じながらも免疫となる。
時代の変化の速さにはその功罪も多々あるだろうが、生きることの原点は何といっても食うことに限るのだ。食糧を担当する農業界は尊ばれてあまりあるのだが、今は、他の業界の覇権争いにしっかり影を潜めてしまった。
都市型文化(川下文化)が農村型文化(川上文化)を呑み込んで常々先行する時代となっている。
食はいのちなり
米はいのちの光なり
などと言えば辟易されるだろうが、人は、コンピューターや宝石を食うわけにはいかない。宇宙旅行のエンデバーの部材を食うことはできやしない。
人は米を食い野菜を食って
初めて完全なるいのちを
培うことが出来る
山があって、川が流れ、
そこに田圃ができて
米や、麦、大豆、そば等の
五穀が育つ田畑が作られる
そして、
働く農人たちがいる風景こそ
ここがいのちのふる里なのだ
心のふる里なのだ
米があって、五榖があって人の世に近代文明を拓き、高度な文化をもたらす原動力となった農人達。
米を神として奉ることが、人が人たる心の調和の生まれる原点ではないのかと自問し、目の前の茅葺き屋根に栄光あれ、と呟く。
風雪に耐え、現代潮流にも負けずに、祖先のエッセンスを大切にして、更に積み上げながら守り通してきた。その中で、生きる喜びを感じ幸せをかみしめてきた。
今後どうなるかは分からないけど、国の文化遺産にならずして、家族の、子々孫々の、時代を超越した快適な文化財として生活実用として、残ってほしいものだ。
その食を作る田畑のことに、心を寄せてくれる人はどれほどおられるものなのか。
「実りの夢」の一節
実りの夢
ここより奥へ入って行っても田圃は見当たりそうもない。この先は林道になっており作業車が刻んだ二本の轍が出来ていた。
一度進入してみたらどこにも回転広場が見当たらない。不安のまま更に奥へ進んで行くとようやく見つかったものの、この路肩は、操作を誤るとたちまち深い谷底に転落する危険があった。ましてや雨上がりのどろどろ道だ。慎重に息を止め、ハンドルを回してやっとの思いで方向転換することが出来た。引き返しを始めてしばらくすると、下の山田から軽快なエンジン音がひびいてきた。
この当たりの田圃は小さく区切られていて形も面積もまちまちの典型的な棚田になっている。小高い丘のような山肌を長い年月をかけて切り崩し、水の落差をうまく利用して完成させている。
つい数年前に読んだ四国地方の棚田のことを思い出した。そこは、百年以上もの歳月を費やして完成されたという。段々畑のような棚田が出来上がるまでには大変な時間と厳しい労力が投入されている。
道具らしいものもなかった時代に、人手を頼りに、生きるための米作りに命を懸けてきた。機械化されたのはほんの三~四十年前のことで、それまでは牛馬こそが耕す天使であった。
農家の人たちは重労働をいとわず、嬉々として一日一日を乗り越えて生きるために死の思いで働き、否、死の代償も含めた秋の実りであったかもしれない。どうしようもない天地大自然を相手に心を癒すためには唄を口ずさみ、見ることのできない神の存在を仰ぎ奉る神事も生まれて来た。天地自然は、人知の遠く及ばざる威嚇に充ちたものであった。
作物を作ることによって生きることができて、定住生活も可能になった。そして、大地にまみれながれも作物の生長に歓喜し、感謝し、生きる幸せを感受してきたことであろう。
やがて家族も増えてゆき、その家族の中から一人二人と外に出て行く。農家から出て行く子孫たちには食糧を提供する。その子孫は、各人の能力の開花となり、やがて、人の生活は多様な都市世界へと変わってゆく。言い換えれば都市も山深い田圃で育って行った末裔たちの集団ということだ。
われわれのふる里は
山があって、川があって
田圃のあるところなのだ
今では、この原初とも考えられるいのちのふる里は、これからどうなることであろうか、若者が寄り付かなくなった。
食うことと、生きるということは別問題のような錯覚さえみえてくる。その食を作る田畑のことに、心を寄せてくれる人はどれほどおられるものなのか。
この山の田圃から米作りの幸せを奪う政治は悪魔の所業に似て恐ろしい。
食はいのちだ
米はいのちの光だ
食は心だ
食乱れて心が乱れるのは
当然の結末であろう
食を守るために、山の中の小さな田圃で、爆音を響かせながら耕している屈託ない農人の姿…
ブルーン…ブルーン…ブルルーン…
と、真っ黒い土の塊を引っ繰り返しながら耕し続けると、この響きで大地もしっかり目を覚ますことだろう。そして、農人たちに豊かな秋の実りの夢をかなえさせてくわることだろう。
ここには山と川と田圃と
そこで働く農人たちがいる
ここがわれらの
いのちのふる里なのだ
烏も、鳶も、雀たちもその鳴き声は変らんようだし、やることも変らんようだし、苦しみ悶えている彼らをみたこともない。
「火食い人種の夢」の一節
火食い人種の夢
人間の創造能力は未来に向けてどんな展開を起こすんだろうかと、人が生きるという次元からそんなことを考えてみた。
まず、人が生きるための食物は全て植物を基本としている。肉食ということもあるが、その肉となる動物たちも植物を食物として生きている。
では植物たちは何を食物として生きているのか。それは、大地(地球)があって、水があって、太陽があるから成長出来るということになる(ここでは微生物たちの活躍は省略する)。
植物たちにとって太陽と大地と水が食糧源ということになれば、私たちが生きるための食物は「太陽の光と土と水」ということになる。即ち、我々は太陽光と土と水のエッセンスを食って生きていることになる。
動物は、この土と水と太陽光を直接に食うことが出来ないから、草木を媒体として生き続けていることになる。
人間の創造力は、突き当たっても突き当たっても、その壁を必ず突き破って成し遂げているようにもみえる。だから将来、人間が生きるための食物をその逞しい創造力によって植物を頼りにせずとも、直接的に、人工化学食品ともいえる食料を作り上げることが出来るかもしれない。
〝土と水と太陽光を原料〟
にして、化学工場で造ることが可能な時代がくるかもしれない。そうなれば、これからの地上生物たちの食物連鎖もその歯車は大きく狂うであろう。
土を用い、水を用い、太陽の光を利用して、種子もいらずにそれらを化学合成して食品化する。これは案外に行けそうな感じもするではないか。
そうなれば、米を中心とする穀物や、野菜や、果実類のいのちの糧は全く不要となる。ここまでくれば四、五千年以上も続いて来た農業は不要とならざるを得ない。
従来、米を植えてきた田圃は、次々と土の生産現場となり、人工化学食品工場とやらへ送り出されて行くことになる。田圃の土が剥ぎ取られた所では、岩盤の肌が剥き出しになって、地球の皮膚が一枚、また一枚と薄くなって行く。
岩石が土になるまでは数万年という歳月が必要であることを思うとき、人工化学食品にもやがてその限界がやってくる。そして、大地からは土壌が消え失せ、次はゴロゴロの瓦礫や、剥き出しの岩盤を土の代用品としてクラッシャーで粉砕することを考える。即ち人工の土を造るということになるかもしれない。
やがて、岩石や岩盤さえも消え失せたとしたら、今度は完全にギブアップとなるのだが、そこは人間のすさまじい英知英才のみせどころだ。掘って掘って掘り進むであろう。今度は最悪だ。火が吹き上げてくるだろう。
人間は必死になって知恵を絞り、その火さえも化学合成しようと考えるかもしれない。こうなったら狂気千万、火食い鳥ならぬ「火食い人種」となるかもしれない。
まあ、考え回すと切りのない世界に落ちてしまいそうだ。空想もここまでくると漫画風だが、しかし、人間の知性は次々と挑戦を繰り返して、生き抜くためには、他の生物には考えられない死闘を繰り広げている。
知性は止まることを知らず、時によっては知性の乱用から生じた知性毒に悩む姿も少なくはないのだ。
人間は、自らの知性によって、一喜一憂、一進一退を繰り返すことが本質なのかもしれない。他の生物たちは、何もせずに昔のままで嬉々とする。烏も、鳶も、雀たちもその鳴き声は変らんようだし、やることも変らんようだし、苦しみ悶えている彼らをみたこともない。彼らは地球進化の次元で鳥は鳥らしく、植物は植物らしく生きているような気がする。人間だって、一昔前までの歴史の中で自然の時間が生きていたはずだ。
小高い山を人の手足を使い、牛馬を使い、やっこらさ、やっこらさと切り崩しながら、長い時間の苦闘を繰り返し、そこに愛らしい小さな田圃の姿を現して、山は次第に棚田となり米を作る田圃に変わった。そして、野生の稲は人間に見いだされ、四、五千年の悠久の時間をかけて、人間の魂となって同化してきた。その永々続いてきた稲の魂と人間の魂は、まさしく霊魂同体といえる。
決して絶やすことのなかった稲の種子は春を待って大地に降ろされる。そして、土と水と太陽の光に守られ、また、多くの微生物たちに守られながら、米の種子はみるみる逞しく緑の姿に変わってゆく。花を咲かせ、秋の実りは黄金に輝かせ、再び人間の心身となって成長をつづける。
人は土を食うものじゃない
火を食う人工化学食品は
夢の中の話でよい
進み過ぎも、急ぎ過ぎも
結果はよくない
自然の流れに同調した時が
もっとも安らぐものだ
地上の草木の緑ほど安らぐものはないし、人は土や石を食うことはやめてもらいたい。
自然の美、輝く太陽…人はもっともっと天に向かい、地に向かい、一度でもいいから頭が下がる思いになったならこの世も本当は最上の平安なのに…。
山があって
川が流れ、田圃が輝き
人の心に潤いと安らぎがある
そこが
いのちのふる里
みんなのふる里なのだ
朝から晚まで経済優先
「ショッカラ節(食から節)」の一節
ショッカラ節(食から節)
〝一呼一吸天の気(呼吸)
一食一排地の気(食事)
天地の気はいのちの食
食はいのちの呼吸なり〟
世の中いかに変われども、食って生きることからの出発だ。食って生きることからの無限の知恵なのだ。
食うことから始まるいのち、そして、知恵の分化、それこそが文化だ。一人一人の知恵が分化して、それが即ち文化となり、その文化は新たな文明社会を創り出す。その根源が食であることを思うとき、食に対し新鮮な喜びと食うことの感動と感謝が生まれる。
その感謝の心は、食のいのちと融合一体となり、天地大自然へとその命脈が直結する。食うことに感謝の心を起こさない人はあまり直結せず、出来る人はその命脈が直結する。その直結力こそ心身の健康に結ぶ力となる。
食を知り、食に感謝して、食を守り、食の愛をうけて生きる幸せを感じてみたいものだ。ここで、食への思いに節をつけてみた。
『ショッカラ節』(食から節)
一、この世は金のかかり過ぎ
それは何かとただすなら
発明発見知恵の華
知恵が知恵生む文明文化
欲がからんで止まらない
止まる薬はただ一つ
食を止めれば直ぐ止まる
いのち止まってこの世の終わり
食を忘れりゃ国滅ぶ
食はいのちの根源だあー
二、この世の情報天地を巡り
テレビ新聞雑誌にチラシ
天地宇宙の果てまでも
コンピューターが駆け巡り
人の欲望かきたてる
踊る阿呆に見る阿呆
食はいのちの根源だあー
どうせ阿呆なら買わなきゃ損損
経済優先止めるには
食うこと止めればすぐ止まる
食はいのちの根源だぁー
三、知識教育頭を磨け
科学は人を神にした
そこで何かを忘れはせぬか
思い止どまるすべはない
知恵の暴走科学のおごり
聖域侵して精液までも
遺伝子銃で操作する
知恵のおごりはあな恐し
食わなきゃ精液つくれない
食はいのちの根源だぁー
四、朝から晚まで経済優先
物質風呂敷ぶら下げて
広げてみたけど大変だぁー
大穴小穴で役立たず
どんどんつぎこむ環境汚染
ざるで水汲むあわれさよ
工業優先拡大消費
鉄はいのちの糧じゃない
食で始まる一日元気
五、守って守って守り抜け
山があって川があり
川のほとりに田圃があって
そこで人間幸せに
足りるを知って生きて来た
春はウグイスホーホケキョ
夏はホタルの光舞い
秋の実りは黄金の稲穂
冬は心の語りぐさ
食はいのちの根源だぁー
六、農業つぶすは人の世を
乱して惑わせ下り坂
天から授かるいのちの食を
守る心が人の道
作る農人真心こめて
いのちにやさしい米作り
食べる我らも自然を愛し
主食の米に感謝する
米が光ればみな光る
米はいのちの根源だぁー
時代は国際分業論が声高に語られ、山村に出かけるたびに殺伐たる思いになった。
「あとがき」の一節
あとがき
平成八年ころ、農村を取り巻く社会情勢はその逼迫の度がいよいよ高まり、農村は暗い渦巻きの中で翻弄されていた。
主食の米を作っても価格は下落し、米余りで減反政策は有無を言わせず、荒れ放題になった田圃には、こぼれた稲籾が自然発芽して草たちと競い合い秋の実りで色づいていた。そんな田圃に振り向く人もすでにいない。時代は国際分業論が声高に語られ、山村に出かけるたびに殺伐たる思いになった。
私は、自然発生した稲籾を採集して何年かにわたり保存したが、その数はあまりにも多く、夏には蛾が大発生する始末。やむなく、ある日全部脱穀して玄米にした。採集範囲は隣県三県を含めた広範囲だから玄米の種類は数え切れない。だから、その食味はいのちの歓喜をおぼえ、最高の気分であった。
私にできることは写真しかない。しかし、文章を書かなければ、思いが伝わらない。どうしたものかと考えたすえにこのエッセー集にまとめたのである。その原稿を持ってある出版社にご検討を願ったが受理には至らなかった。
その後、他の出版社に折衝する気にもならず、月日は早や七~八年過ぎ去った。今、改めて写真集を出す予定で進めている中、どうも気になるこのエッセー集を取りだしてみれば、その内容の本流にはなんら変わりも無い自分に気がついた。では、もう一度その気になって、当時の文脈文体をそのまま訂正せずありのままに出してみることにした。
農村をとりまく時代変遷の一証左となれば幸いである。
菅原 茂
目次
まえがき
田圃の目覚め
村人のいない 村長さんと助役さん
或る農人のルーツ
雪は水の眠り
答えなき沈黙の声
名画『いのちのふる里』
山も川もいのちの先祖
調和の美
いのちのスクリーン
白い弓矢は米の花
自然智
踊るブナの木
米は大地の光
米はいのちの玉手箱
山の海
悟境のふる里
食い改めて百歲長寿
時代
数霊に秘める「万物普遍のふる里」
祖先のエッセンス
実りの夢
山田の青大将
火食い人種の夢
ショッカラ節(食から節)
春を告げる雪の鶴
水は若さの秘訣
消してならない農人魂
水はいのちの旅人
カエルの応援団
ふる里の原風景
減反休耕田の稲
蓑笠父さんにつづけ
火と水はいのちのふる里
いのちのふる里談義
木製衛星「エウロパ」と減反休耕田
稲の受粉にふる里を見た
浪曲『私は野生の二年生』
お米の女王
雨ガエルのふる里
あとがき
スライドで閲覧
図書館で
所蔵図書館一覧を掲載しています。
都道府県別の横断検索ができます。
ほかの著書
米(食物・自然界)の生命愛に身も心も重ねることで、波乱万丈な人生もどんなに苦しい思いも澄み切ったものへと昇華した著者夫妻。その二人が遭遇した共振共鳴共時の記録は、「こころとは」「いのちとは」という命題に対する答えの証しです。